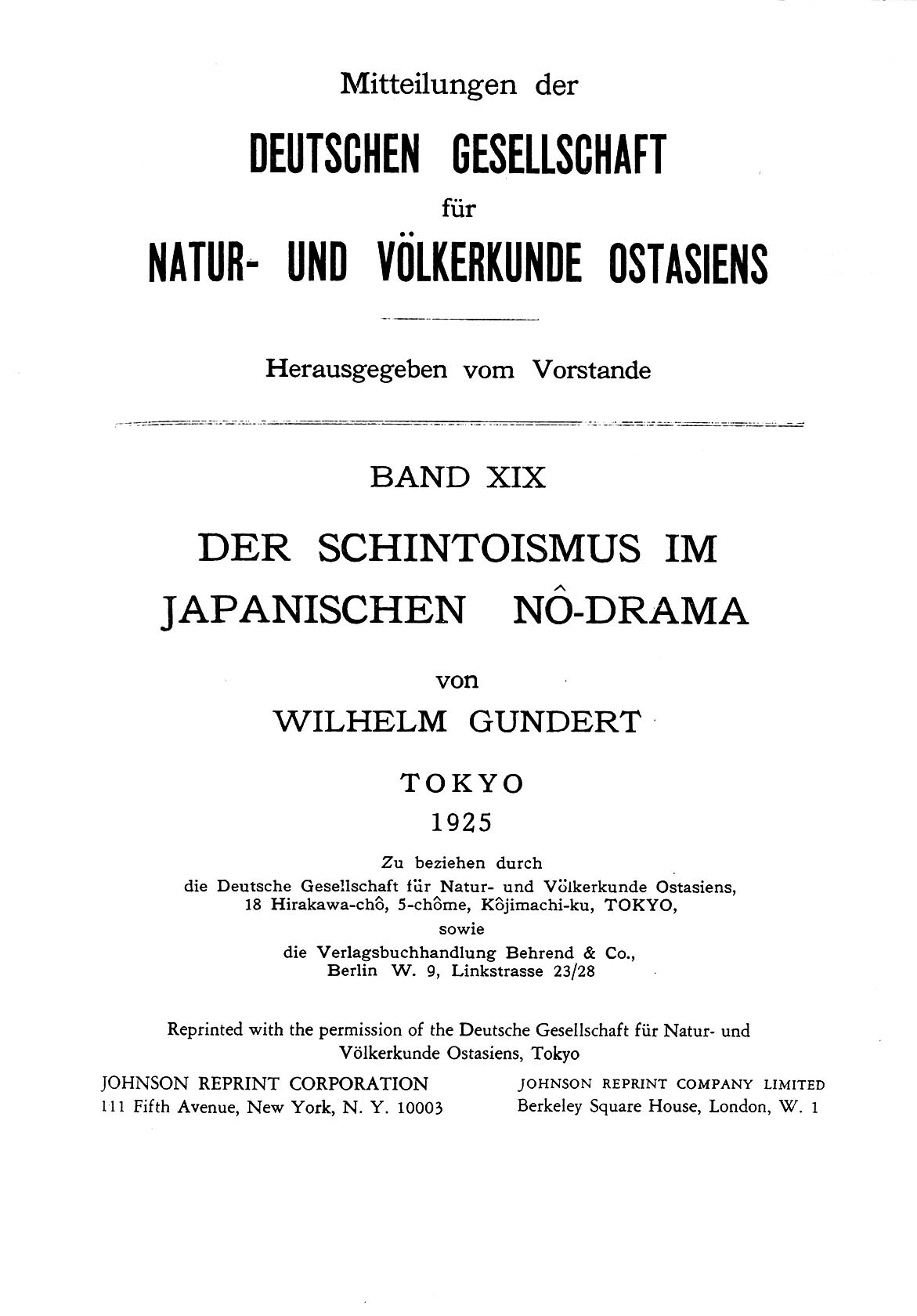村松郷土史研究会会員 渡 辺 好 明
ヴィルヘルム・グンデルトWilhelm Gundert(1880~1971)はドイツのノーベル賞作家で詩人でもあるヘルマン・ヘッセ(1877~1962)の従弟で、ハレ大学とチュービンゲン大学神学部で神学と哲学を専攻してキリスト教伝道者となった。1904(明治37)年に内村鑑三の『余はいかにしてキリスト教徒となりしか』を翻訳出版し、06(同39)年26歳の時に内村を頼って来日、56歳まで、途中2年間帰国しているものの、日本に約30年間滞在した。そのうち、新潟県村松町(現五泉市のうち)に5年間住んで伝道を行い、ほかにも第一高等学校や熊本第五高等学校、水戸高等学校でドイツ語の講師を勤めた。そして村松町時代から日本の文化や宗教を研究するようになり、一時帰国してハンブルク大学で学んだ。ふたたび日本にきて、水戸高等学校の講師時代に「日本の能楽における神道」の論文を書き、これをもってハンブルク大学で哲学博士号を取得した。さらに日独文化協会の主事として日本とドイツの文化交流に尽力し、帰国後は日本学の権威となって、ハンブルク大学教授、および哲学部長、総長、副総長を勤めた。名著といわれる『東洋の抒情詩』を出版し、晩年には『碧巌録』を翻訳出版してその業績を確かなものとした。
グンデルトが謡曲に初めて触れたのは村松町でキリスト教を伝道していた時代(1910~15)で、歯医者の信者佐藤久吾に習ったのが始まりである。1915(大正4)年6月に、グンデルトを中心に村松夏季学校が開催され、新潟医学専門学校の基督教青年会員10名、盟友の宍戸元平とヨシコ夫人、大鹿教友会の木村孝三郎、地元の医師石川林益、佐藤久吾、グンデルト夫人のヘレーネが出席した。これに参加した矢高行路が、手記『冬の桑園』(星野慎一「グンデルト先生と村松町」より引用)の中で、次のようなエピソードを紹介している。
或る夏、聖書舎のグループが一緒に旅行したことがあった。田舎の小さな温泉宿に泊まった
。それは冷泉をわかしたもので、木造の湯舟も古く、白濁りの汚い、日本人の我われでも一寸
入るのを躊躇するくらいのものだったが、先生は平気な顔で皆と一緒に入っておられた。
湯から上がって、先生は謡曲のけいこをはじめた。師匠は歯医者の信者であったが、旅先で
本をもっていないので、時どき文句につかえる。たしか「紅葉狩」だったと思うが、師匠がつ
かえると、弟子のグンデルト先生がずんずん先を云って行く有様であった。
もっとも、後に「謡曲に現われた日本の宗教精神」とかいう論文で、ドイツの文学博士をと
られたくらいで、素晴しく勉強しておられたのであった。
当時の村松町は村松藩3万石の旧城下町で、グンデルト一家が移住した1910(明治43)年の人口は9433人であった。村松町では能は江戸時代から盛んにおこなわれ、梁取耕平の「村松の謡曲」(『郷土村松』第27号)には、大正時代、昭和時代の活動ぶりが書かれており、観世流の流れをくむ村松鶴諷会の会員は、昭和56年現在82名におよんでいる。
なお、吉田東伍が1908(明治41)年に発見した『世阿弥十六部集』の旧蔵堀子爵家をこの村松藩主堀家とする推論を、筆者(渡辺)がインターネットで「『世阿弥十六部集』家蔵堀子爵家について」と題して発表しているので参考にされたい。
1920(大正9)年にグンデルトは祖国が第1次世界大戦に敗北したため、同胞と苦難を共にしようと思って一度帰国した。そこでグンデルトは博士号をとるため、21(同10)年に勉強の機会を調べていると、ハンブルク大学でカール・フロレンツ教授が彼を引き受けてくれた。そのためグンデルトは10月25日にハンブルクに到着した。
フロレンツは非常に好意的で、専攻科目の日本学の他にも、同じくらいに宗教史や哲学について、博士号取得のための助言を与えてくれた。
フロレンツ(1865~1939)は東京帝国大学で25年間、ドイツ文学とドイツ哲学の教授を勤めた。1914(大正3)年にドイツに帰国し、のちにハンブルク大学で日本学教授となり、ドイツにおける日本学の祖となった。日本の宗教を研究した『神道の歴史的起源』、『日本古代の宗教儀礼』、日本神話研究の『日本の神話』、日本文学研究の『日本文学史』、『現代日本文学』、『古今集用語辞典』、日本史研究の『日本年代史
五九二―六九七年』などの著書があり、今日にいたるまで学問的に高い評価をえているという。ほかにも日本における国文学研究の近代化や、ドイツ文学研究の発展に貢献したという。そのためグンデルトは、この日本の精神史において神道の役割を重視するフロレンツの影響を強く受けている。
そしてフロレンツの教え子のドイツ文学者に、小牧健夫、吹田順助、茅野儀太郎(蕭々しょうしょう)、桜井政隆、小宮豊隆、木村謹治らがいる。またドイツ文学者ではないが、『広辞苑』を編纂した新村出(言語学科)や芳賀矢一も門下生であった。
グンデルトは博士論文「日本の能楽における神道」を書く前に、この研究の周辺の材料を使って論文「神道」と「日本の仏教」を書き、翌1922年に日本でドイツ語の雑誌『東洋の光』に発表した。それはただ資料から抜き出しただけでなく、自分独自の見解をつけ加えて人々の関心を集めたので、博士論文に対する確信を深めることができた。
ふたたび来日したグンデルトは、水戸高校時代(1922~27)に汽車に4時間ほど乗って、わざわざ東京の猿楽町にあった宝生会の能楽堂へ、能の鑑賞のため通ってきていた。そしてグンデルトはここの能楽堂で謡曲の本を開いて見ながら、熱心に見物していたという。東京帝国大学の哲学科教授桑木厳翼(げんよく)とは、このころ知りあった。
桑木厳翼は1874(明治7)年生まれの哲学者で、99(同32)年に第一高等学校の教授兼東京帝大講師となり、1906(同39)年に京都帝大の教授となったが、翌年からドイツなどに留学し、グンデルトとはすれ違っている。そして14(大正3)年から東京帝大の哲学科主任教授を勤めていた。宝生流の謡曲が趣味であった(東京書籍『近代日本
哲学思想家辞典』による)。
グンデルトの300頁近い論文「日本の能楽における神道Der Schinto ismus im jspanischen Nō-Drama」(「日本の能楽に於ける神道精神」、「謡曲に現われた日本の宗教精神」とも訳されている)は、OAGドイツ東洋文化研究協会が1925(大正14)年9月に発行した『ドイツ東洋文化協会報告19』に発表され反響を呼んだ。論文はこの年ハンブルク大学日本学科に提出され、グンデルトはこれによって哲学博士号を取得した。この緒言の終わりに、「一九二五年正月水戸にて W・グンデルト」とある。この本は国立国会図書館、ドイツ東洋文化研究協会、茨城大学図書館に所蔵されている。
「日本の能楽における神道」はドイツ語で書かれ、日本語訳がまだないため、一般の読者は読むことができない。しかしこの論文について日本人が書いた紹介文や論文を読めば、あるていど内容を知ることができる。
このドイツ語論文をはじめて日本語で紹介したのは桑木厳翼のようである。彼は論文が発表された17年後、『宝生』1942(昭和17)年1月号(宝生発行所)に「能楽研究の一書――『日本の能楽に於ける神道』に就て――」と題して、4頁にわたり紹介している。
ここで桑木はこの論文を、「既に広く世に知られて居る訳であるが、然し必しも好謡家一般に読まれては居ないと思ふから、此雑誌などに記録して置くことも亦無用ではないであろう」という動機から採りあげたという。これは論文の価値もさることながら、その後の日本の政治や精神的思想的状況と無関係ではあるまい。それについては後述するが、ともかく、これにより、このドイツ語論文が日本人にも注目され、広く読まれていたことが理解できる。
グンデルトがこの研究をはじめたころは、日本では能楽に関する研究書もまだ少なく、本文は大和田建樹の※『謡曲通解』により、ほかは※吉田東伍校註の『世阿弥十六部集』や、そのほか謡曲註釈、国文学史、神道と仏教の参考書などしかなかったという。したがってそれまで日本において能楽の註解研究のようなものはあったものの、日本人が本格的に能楽の本質を論じたものはなかったようである。
※『謡曲通解』は1892(明治25)年に博文館から発行された。
※吉田東伍は新潟県安田町保田(現阿賀野市保田)の出身。東伍の妻かつみは、グンデル
トの協力者木村孝三郎のいた大鹿の吉田耕次郎の長女であった。吉田東伍校註の『世阿
弥十六部集』は、1908(明治41)年発行の能楽会版と、1918(大正7)年発行の磯部
甲陽堂版がある。
次いで「日本の能楽における神道」について、1962(昭和37)年に東京女子大学の古川久一が、自著『欧米人の能楽研究』(東京女子大学学会)の中で、「第九章 グンデルト」として16頁にわたり紹介している。
それによると、グンデルトはハンブルク大学での師フロレンツの神道研究に拠りながら、パウンド・ウェーリーや、N・ペリーの能楽論を参考にこの論文を書いたという。能楽には神道以上に仏教の影響が強いが、それを扱うことを断念し、別の機会に譲るとして、本論ではあえて神道的性格に限定して論じた、と見ている。
そして能楽の特色を「寂び」の理念から捉え、「〈寂び〉という翻訳し難い言葉によって適確に現わされるような、少しの飾りもない簡素と洗練されきった趣味との間に独特な総合が成就された」といっている。そしてこの「錆びたもの、古いもの、苔蒸した石、朽ちた幹、くすんだ色、嗄れた低音」などが表現している美を、能の精神と考えた。
そこから「暗示していることに通じなければ、舞台に起っていることは決して分らない、というのは、すべては暗示されるだけだからである」と述べて、能の暗示性(象徴性)に触れる。さらに能楽は古代神話を「神秘」の露呈という形で復活させるものであるとして、キリスト教神秘主義の思想を援用して、能楽の宗教的特質を深いところで捉えようとした。
また、古川は別のこところで、この論文がのちにフランス人ルノンドーに、「能に於ける仏教思想」を書かせるもとになったといっている。
1967(昭和42)年になって、東京大学教養学部外国語学科の『外国文学研究紀要』第15巻第2号(同学科編)を1冊全部使い、新田義之が「ヴィルヘルム・グンデルトの謡曲研究」で論考している。この論文はグンデルトの生存中に発表されたので、したがって彼も読んでいる。グンデルト自身がOAG会長ロベルト・シンチンガー教授を通じて新田に送った主要著作目録と注を入れて52頁におよび、巻末に3頁のドイツ語による「ヴィルヘルム・グンデルトの能楽研究WILHELM
GUNDERT UND SEINE NŌ‐ FORSCHUNG」を付録として載せている。
新田論文によれば、グンデルトは、日本人の民族的性格を、「西洋においては象徴という概念でようやくその片鱗をうかがっているものなのだが、その世界を日本人は非常に早く、ヨーロッパ的意味での論理を辿ることの不得意さという弱点を逆に長所として働かせて発見した」として、高く評価したという。
また、グンデルトは掛詞に謡曲の芸術的本質を発見し、「ドイツ語においてはとても耐え切れるものではない非文法的なつなぎ方で、これら日本語の詞句が連なって行くのだが、これこそ謡曲作家が言語美の微妙さに酔い痴れて行く典型的な姿であって、この言葉のハーモニーの中では事件の叙述はほんのほのめかしに止まる一方、情調は、一層豊かに、色彩にあふれたシンフォニーをかなでるのである。(中略)ここでは実際、文法や論理はもはや通用しないのであり、言語の背後にあって意識の周辺にただようイメージや情調を想起せしめるものへの恍惚たる陶酔が主眼なのである(以上グンデルトの文章)」と指摘している。
そして新田は、「肯定も否定も共に包み込まれ、主客の対立も解消し、前文の意味の流れは次文の中に、いつとはなく何処でとはなく吸収され流れ去って行く。あらゆる現世的論理、主張、葛藤を止揚した世界がここに現出する」と理解している。
そこで、「グンデルトは謡曲の中に神道と仏教の融合の姿を追求して、そこに日本人の民族的特質を見究めようとしたが、その過程から必然的に日本人の芸術の理解に導かれ、そこに真に評価すべき価値のある日本精神の粋を見出した」という。この「芸術の中にのみ存在し得る世界こそ、論理的厳密さにこだわるヨーロッパ的知性には決して生み出せないもので、この世界をここまで純粋に結晶させたところに、グンデルトは日本人の民族性格を積極的に評価するのである」としている。
新田は神道や能のような、特殊な日本の精神文化の本質を、グンデルトが会得していたことに着目する。しかしこれをグンデルトがよく勉強して異文化を自分のものにした、というようにとるだけでは、グンデルトを理解することにならない。彼がキリスト教神秘主義思想の深い伝統に立っていたことを弁えないと、晩年にキリスト教へ回帰した意味が捉えられない。
1978(昭和53)年には片岡美智が、「〈能〉への二つのアプローチ――N・ペリーとW・グンデルトの対照的な『三輪』観――」を『京都外国語大学研究論叢18』(同大学総合研究所編)に発表し、1935(昭和10)年に発表されたフランス人ノエル・ペリーの著書『能』と、グンデルトの「日本の能楽における神道」に取り上げられている演題『三輪』についての解釈の相違を論じている。
ペリーの『能』は1944(昭和19)年に日仏会館から刊行されたものだが、これは1909(明治42)年に発表された『能楽研究序説』、1911(同44)年から1924(大正13)年にかけて発表した注釈つきのフランス語訳謡曲と狂言を集大成したものである。したがってグンデルトはこれらの全部か、あるいは一部を参考としている。ペリーはグンデルトより15歳年長で、17年早く1889(明治22)年に来日した。
宣教師で音楽教師でもあったペリーは、能を楽劇とよび、物語と音楽、舞を兼ねそなえた文学として最高峰のものとし、「謡曲の趣向が一種の象徴文学である」と位置づけ、能は日本精神と日本の宗教思想の把握を可能にしてくれると考えた。しかし片岡はペリーのことを、「彼本来の宗教的資質が彼を浪漫性の強い神秘家に育てあげるよりもむしろ、熾烈な克己の精神・苦行の情熱に身をゆだねる高度な倫理性の持主たらしめた」と見ている。
この片岡の全体で31頁の論文は、ほぼ前半がペリー論、後半がグンデルト論となっている。
片岡の紹介によると、ペリーは1904(明治37)年の『能楽』6月号に、「能楽は日本文学の最大なるものなり」と題する談話を寄せ、当時の日本の文学者が欧米の文化に心酔し、自国の文化を顧みないことに反省をうながした。この談話は心ある日本人に衝撃を与え、すぐさま早稲田大学内に「能楽文学研究会」が結成され、高田早苗、坪内逍遥、池内信嘉、ペリー、久米邦武、芳賀矢一、吉田東伍、五十嵐力、東儀季治、藤岡作太郎、伊原敏郎らが参加して、日本人による本格的な能楽研究の運動がはじめられたという。
しかしグンデルトの能楽論を、日本ドイツ学会の辻朋季はつぎのように批判する。
辻の指摘する「グンデルトには日本文化をエキゾチックなものと捉えたり、日本文化に特殊性を読み込んでことさらに美化したりする傾向が強い」という面については、筆者はグンデルトの書いたものを十分に読むことができないため、否定も肯定もできないが、辻のグンデルトに対する指摘も、あながち不当な中傷ともいい難い。
1926(大正15)年4月23日に、グンデルトは東京神田錦町の学士会館に招かれ、「日本の能楽に就て」と題する講演を行った。これは前年に発表した論文が注目され、学会の加藤玄智(げんち)博士が招いたと推測されている。
この日本語の講演の内容は、1927(昭和2)年の6月と7月に、『聖徳記念学会紀要』第27巻に10頁分が、および第28巻(第28巻は国立国会図書館で欠号)にドイツ語で「講演 欧文欄 日本の能楽に関する新研究」として発表された。
この論文については、1979(昭和54)年にいたって関根俊雄が「グンデルトの能楽本質論」と題して、『跡見学園短期大学紀要』第15集(同大学学術委員会編)で注を入れて26頁にわたり論じている。
関根論文はグンデルトのドイツ語報告の前文のごく一部を除き、ほぼ全文を逐語訳で載せているのでその内容を知ることができる。
それによると、グンデルトは「能楽が、日本的精神による特に傑出した所産であり、その本性において何か独特なもの」であるといい、「能楽に日本的精神の本質が開示されている」と見ている。そこで、能楽に現われた神道の聖なるものや、共同体としての日本の神による守護、能の舞のシャーマニズム的な霊的恍惚やディオニソス的性格に注目する。そこから神道の本質を、「神道は之を要約すれば国民的組織体たる日本に対しての宗教的尊重、近代用語を用いるならば日本自体への信仰」であるとして、「天つ日嗣」の君主(=天皇)の統治の正当性にも言及する。
またグンデルトは芸術と宗教の一体性についてふれ、「能はその全体的な本性からして分裂と崩壊とが起らず、むしろ各領域が特に宗教的要因を中心として、すべて一体となっている中世的な精神段階に属している」と述べている。これを関根はゲーテの言葉をひいて、芸術と宗教は「概念によらざる世界把握である」と解説する。
ここでグンデルトは、宗教の本質論をドイツのプロテスタントの神学者・宗教学者ルドルフ・オットー(1869~1937)の『聖なるもの』(岩波文庫に収められている)によったと述べているので、関根ははじめの4頁をさいて、この本の解説を行っている。
オットーは『聖なるもの――神観念に於ける非合理的要素並びにその合理的要素との関係について』で、宗教そのものの本質を明らかにしようとした。
彼はラテン語のヌーメン(明確な表象をとるにいたらない超自然的存在)という語から作られたヌミノーゼ(聖なるもの)という語を使用する。ヌミノーゼは日本語の「神明」や、能楽に出てくる「神さびわたる」に相当する。これは清浄、厳粛、偉大、畏怖、懐かしさ、神秘的などの感情が一つになった原始的心境をいい、これこそが真の宗教精神であるという。つまりすべての宗教の本質は、教えや道徳のような理性的要素の中には存在せず、むしろヌミノーゼに対する非理性的な畏敬の感情にあると主張する。
ヌミノーゼの本質は、戦慄すべき秘儀の感情によって示唆される。この感情は静かで深い瞑想的気分をただよわせることもあるが、時としては、「激変して急激に心を破り出ることがある。また時としては、不可思議な興奮と陶酔と法悦と入神とに導くことがある。それは荒々しい悪霊的な形態を持っている。それはほとんど、妖怪のような恐怖と、戦慄とに引き沈めることがある。それはなまなましい、粗野な前階と表現とを持っているが、しかし発展しては美わしい、純粋な栄化されたものとなる。それは被造者の静かな、へり下った戦慄と沈黙とになることがある――何の前で? すべての被造物に超越し、言い表し難い秘密の中に存在する者の前で」と書いている(岩波文庫『聖なるもの』)。
グンデルトは原語のヌミノス(ヌーメンの属格)をディオニソス的な心情と解釈した。そこから「清浄な、厳粛な、偉大な、絶対的な境地に入って有頂天となった心の陶酔状態」が派生し、これこそが現実世界を脱却して宇宙全体に和合した「神明」の天地、「神さびわたる霊域」が出現した境地であると考えた。
また彼は能の舞を、この芸術の特質を決定する中心的なものと考え、それが神秘的な酩酊と、宗教的、芸術的な霊的恍惚によって、世俗を超えて神聖な境地へと高揚するディオニソス的芸術であると主張した。
しかしグンデルトのいうヌミノスは、基本的にはオットーからきているので、「神明」や「神さびわたる霊域」も根源には「戦慄すべき」ものが潜在していることになる。
そしてグンデルトは、能の舞台では神は「すべての人・物の光」であり、「天地に遍満する所の神気の〈通力〉、謡曲でいうところの宇宙全体の〈瑞現〉」であって、これこそが純粋唯一の宗教であるといい、能楽が高度な芸術であるのはそのためであるという。グンデルトは能楽の中に、日本人の宗教的心象や興奮が、原始的な純粋さで保たれていることに感嘆する。
グンデルトの論文を贈られたオットーは、「この能ドラマは日本の精神的なること及び深遠なることにつき見事なる感銘を与える。ヌミノーゼの要素がいかに強くこの戯曲に現われているかに驚く。これは実に全く私の象徴のための模範的カルテである」といい、自分の考えた宗教観が、日本に古くから能楽として精神文化の中心に位置していることに対し、「真に日本は驚くべく又怖るべき世界唯一の勝れた国である」と驚嘆している。
「日本の能楽における神道」の発表から10年後の1935(昭和10)年になって、グンデルトはドイツ語の論文「世阿弥における幽玄の概念Über
den Begriff〝Yūgen〟bei Seami」(『ドイツ東洋文化研究協会報告25』所収)を発表した。古川久一の『欧米人の能楽研究』によると、グンデルトが当時まだ世阿弥の主著『花鏡』(『世阿弥十六部集』では「覚習条々」または「異端」としている)の所在がようやく知られたばかりのころに、難しい幽玄の概念を考察していることを評価している。
グンデルトは久松潜一や野村八良の幽玄の変化についての研究をふまえながら、ウェーリーが幽玄を禅に由来すると見たのは正しいかもしれないが、世阿弥の幽玄はやはり歌学からきていると主張した。
グンデルトは「日本人の概念をドイツ語に翻訳することは、まず全く不可能である」としながらも、能楽の最高原理である幽玄の概念を分析し、そこに時間的と非時間的の「二義性」(古川の用語による)を発見する。時間的な側面が、「日本人の精神史の流れの中で決定される美的理想の変化によって制限された」ことを見てとり、非時間的な面に「神秘的なものに連なるところのものすべてを包含して」いると見ている。しかし、「これについての真の概念は、決して言葉では仲介できない」と断っている。
そして古川はこの論文が、その後ドイツにおける世阿弥研究が盛んとなるきっかけになったと書いている。
ハンブルク大学の日本学研究科の在任中(1936~45)、グンデルトは『源氏物語』を独訳して有名になったオスカー・ベンヌル教授や、ドイツきっての日本語言語学者ギュンター・ヴェンク教授など、多くの優れた研究者を育てた。ベンヌルはほかにも志賀直哉や芥川龍之介、谷崎潤一郎の小説なども翻訳しているという。
またベンヌルはグンデルトの影響で能の『世阿弥元清の二編の後期著作Zwei Spätschriften Seami Motokiyos』を1952(昭和27)年に出版し、翌年には世阿弥入門または能楽論概要というべき『世阿弥元清と能の精神Seami
Motokiyo und der Geist des Nō‐Schauspiels』を出版している。
1961(昭和36)年にいたって、大阪外国語大学教授のドイツ人ヘルマン・ボーネルは、自著『習道書・去来華Shū‐Dōsho:Kyakurai‐Kwa』をグンデルトに捧げ、献辞を「日本についての知識と認識とに不偏妥当さを振興したことに於いて、ヴィルヘルム・グンデルトのような、確乎たる、精密な、数十年来辛抱強く活動してきたドイツ人に、敬意を表して献題して捧げるのには、例えば、偉大な能の創作者、理論家であり、最年少期から高齢期に至るまで努力し、絶えず錬磨を重ね、天才的な作品を創造し、その作品を自身上演し、未来への指示を与えたこの卓抜の人、世阿弥の著作ほど、より適切なものは恐らくないであろう」(『欧米人の能楽研究』)と書いて、最大級の賛辞を惜しまなかった。
ボーネル(1884~1963)はハレ大学とエルランゲン大学、チュービンゲン大学で学んだグンデルトの後輩で、第1次世界大戦の際に捕虜となり、鳴戸の板東俘虜収容所にいたが、解放後も日本に残って日本文化の研究と紹介に努めた。彼は大阪に40年暮らし、大阪外語学校の講師から教授となり、グンデルトの生涯の友人でもあった。聖徳太子や、北畠親房の『神皇正統記』に関する研究ののち、能楽に関心を向け、世阿弥の作品を数多く翻訳し、彼の芸術論を研究した。グンデルトはこのボーネルの『聖徳太子』の書評を書いている。
日本語に堪能なグンデルトは日本語で能を鑑賞しており、能の翻訳は楽しんでやっているが、「日本人の概念をドイツ語に翻訳することは、まず全く不可能である」といっているように、一筋縄にはいかなかったようだ。水戸時代に博士論文を書いているあい間に、彼は一日『賀茂』のある箇所を翻訳してみた(『ヘレーネ夫人の回想録』より反訳)。
合唱団が歌った:
それは誰でも知っている! 老人の登場
太陽は即座に暗くなって。
夢に描いた〈現実〉がまもなく生じて漂った。
それゆえゆっくりと私たちの形成する光景が行く――
それは存在しそしてそれにも関わらず濁ることなく!――川の流れによって、
その清き流れを我々は汲み取る、その結果天の創造神の
心情と価値が自から我々の上に流れ込む、
そうなのだ、神はふさわしく現れて我々をここに掬い取る。
天国の乙女(登場して神に告げる):
彼の来る時間が迫っています:
そうする時一つの流れの中に信仰を見出す、
さらに驚嘆すべき神が歩いて登場
すばらしくも壮麗な恩寵にあふれる光景が
我々の目の前に顕現する。おおこの神の恩寵よ!
この神の歩みに引き続き:
私はそれで御所を守ったのだ、
主人と分身は役割をそれぞれ持っている。
私は別雷の神である。
(中 略)
神:
黒雲の在処の気高い天国で、そこから彼は
風と雨を自在に時間に合わせて投げつけた
別雷が分裂した、
激しく己を黒雲と霧をつらぬいて打ち鳴らし。(以下略)
日本人でも難解な能を外国語で伝えることは難しい。グンデルト訳は説明を加えてかなり意訳となっており、原文と逐語訳するのは困難である。生涯にわたって天皇をこよなく崇拝したグンデルトにとって、『賀茂』は恰好の題材でもあった。御所と天皇を守る別雷は、また、雨を降らせて五穀の豊穣をもたらす神であった。そしてこの神は旧約聖書に出てくる創造神エホバのように、幸いと同時に災いをもたらす両義的な存在でもあった。原始的な神の摂理は現世の人間の善悪の観念を超越している。従兄のヘッセもエッセイ『カラマーゾフの兄弟、あるいはヨーロッパの没落』の中で、この両義性の併存こそが、近代ヨーロッパが失ったアジア的理想だといっているが、ヘッセが能について書いたものはなさそうである。
(この論文は2017年9月発行の拙著『ヴィルヘルム・グンデルト伝』(私家本)の記事をもとに 構成したものです。2018年12月18日up)